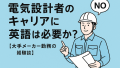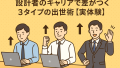設計者のキャリアを左右する最大の要因は「努力」よりも「部署選び」です。
同じ能力を持っていても、配属された部署によって昇進スピードや出世ルートは大きく変わります。
まず理解しておきたいのは、
- 忙しい部署は確実に出世できるが、年功序列を崩すのは難しい
- 暇な部署は出世枠が少ないが、能力があるほど年功序列を崩しやすい
という基本構造です。
さらに、暇な部署では「仕事をやりたがらない人」が一定数存在します。その結果、部署全体の仕事をほぼ一人でこなすことになり、その功績で一人勝ち的に出世するケースすらあります。
ここから、設計者が部署戦略を考えるうえで重要なポイントを具体的に解説します。
出世の仕組みは部署単位で決まる
多くの企業では「10部署で5人を昇進」といった形で枠を決め、最終的には部長同士の話し合いで人事が決まります。
このとき、発言力の強い部長がいる部署は有利です。影響力のある部長は自部署に「2〜3枠」を持ち帰ることができる一方、弱い部署はほとんど出世者が出ないこともあります。
つまり、昇進は「個人の能力」だけでなく、所属部署の力学と部長の影響力で決まるのです。
忙しい部署でのキャリア
忙しい部署は会社にとって重要度が高く、多くの案件を抱える環境です。その特徴は以下の通りです。
- 部長の影響力が強い
会社に欠かせない部署であるため、部長の発言力が大きく、昇進枠を多く確保しやすい。 - 他部署との交流が増える
勤務時間が長く、他部署と接点が多いため、推薦をもらえる可能性も広がる。 - 差別化が難しい
全員が長時間働くため「突出した成果」を示すのが難しい。結果として昇進は堅実に進むが、年功序列を崩すことはほぼできない。
👉 忙しい部署は、確実に昇進したい人向けの堅実ルートですが、若手が抜け出して早期出世するのは困難です。
暇な部署でのキャリア
暇な部署は案件数が少なく、余裕のある環境です。その分、昇進の仕組みや可能性は大きく変わります。
- 出世枠が少ない
1年に1人、少ないときは2年に1人程度しか昇進しないこともある。 - 差をつけやすい
仕事量が少ないため、成果の差がはっきり出る。部署内で一番を取れば、昇進チャンスを独占できる。 - 仕事をやりたがらない人が多い
暇な部署ほど「できるだけ楽をしたい」と考える人が多い。その結果、一部の人が部署全体の仕事を担うことになり、自然と評価が集中する。 - 年功序列を崩しやすい
成果の差が明確に見えるため、若手でも年功序列を飛び越えて昇進できる可能性が高い。
👉 暇な部署は能力がある人にとっては「年功序列を打ち破るチャンスの宝庫」です。逆に能力が平均的だと出世の機会がほとんど巡ってこないため、二極化が起こりやすい環境とも言えます。
海外経験は経営層への切符
さらに経営層を目指すなら、海外経験が非常に大きな意味を持ちます。
- 海外駐在や海外プロジェクトを経験すると、それだけで「経営人材」として評価されやすい
- 本社復帰後に昇進ルートに乗るケースが多い
- グローバル感覚があることで、経営判断に関わるチャンスが増える
👉 設計者にとって海外経験は、一気に経営層に近づく最短ルートと言えます。
設計と営業の違いに注意
ここまで設計者の話をしてきましたが、営業は評価の仕組みがまったく違います。
- 営業は「数字」で評価されるため、どの部署にいても成果が見えやすい
- 成績を出せば部署を超えて昇進が可能
- 設計のように部長や推薦に左右されにくい
👉 設計は成果が数字で見えにくいため「部署の影響」が大きいですが、営業は数字が全ての世界。この違いを理解しておくことが重要です。
まとめ|部署戦略がキャリアを決める
設計者がキャリアを築くうえで、部署選びは極めて重要です。
- 忙しい部署:確実に出世できるが、年功序列を崩すのは難しい
- 暇な部署:出世枠は少ないが、能力があれば一気に抜きん出て早期出世が可能。部署全体の仕事を任され、一人勝ちになることもある
- 海外経験:経営層に近づく切符となる大きなキャリア資産
- 部長の影響力:推薦人事の場で部署の出世枠を左右する
設計者にとって「努力」だけでなく「どこで戦うか」を見極めることが、キャリア戦略の要となります。
今回設計者のキャリアは部署で決まるという話をしてきました。
部署配属後、実際どのように出世していくかの体験談を紹介した記事もあります。
あなたが出世のために具体的に何をすればよいか困ったときは参考にしてください。